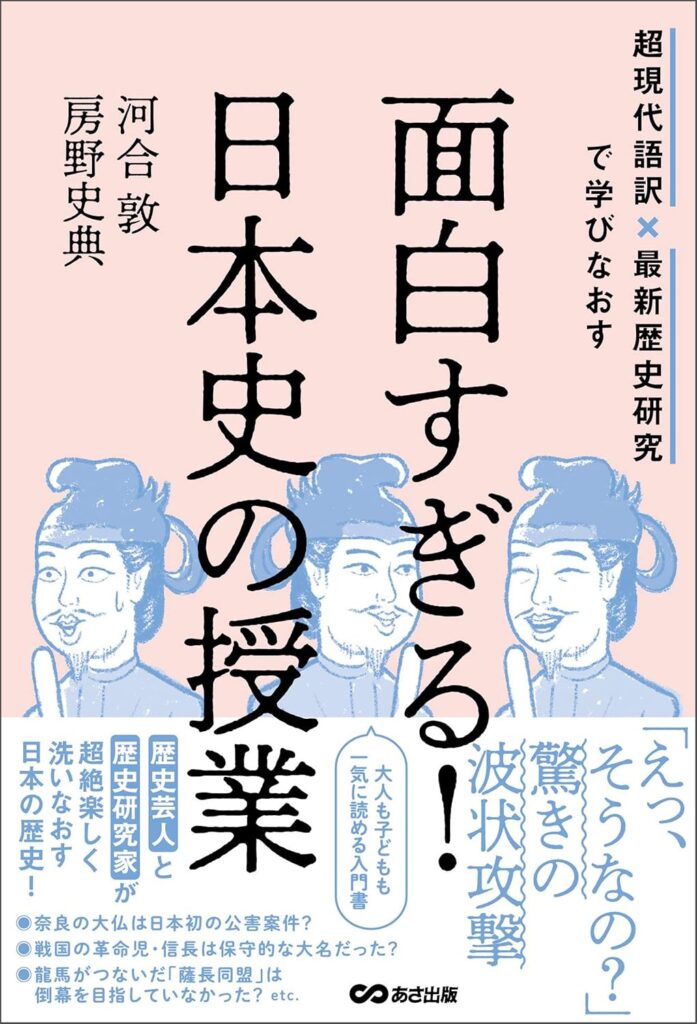【番組感想】NHK歴史探偵「江戸の仕事人たち」出版と飛脚の驚くべき技術とは?
2025年5月7日放送のNHK『歴史探偵』では、「江戸の仕事人たち」と題して、江戸時代に活躍した職人たちの技術と誇りに迫る特集が放送されました。特に今回は「出版」と「飛脚」という2つの仕事にフォーカスし、現代に通じる知恵や工夫を解き明かしていました。
江戸の出版文化:驚きの職人技と遊び心
● 江戸は出版大国だった?
江戸時代、本の出版数は100年で約4倍にまで増加。当時の庶民の読書熱がうかがえます。神田の古本屋では、喜多川歌麿の作品や、蔦屋重三郎による版元「耕書堂」が発行した多彩な書物が紹介されました。医学書や旅行ガイド、絵入り物語などジャンルも豊富でした。
● 印刷の裏に隠された超絶技巧
木版印刷の現場では、髪の毛のように細い線を彫る「毛割」など、極限まで精緻な技術が求められました。版木の彫り方ひとつにもこだわりがあり、滑らかな印刷のためにあえて“台形”に彫るなどの工夫も。
伝統工芸士・永井紗絵子さんが「偐紫田舎源氏」の版木を復刻する様子では、職人たちの“狂気とも言える”こだわりが再現されていました。
● 再生紙と米粉が支えた出版
江戸時代の紙には、なんと人の髪の毛や米粉が混じっていたことが顕微鏡分析から明らかに。限られた資源を最大限に活かす再生紙文化も、出版を支える一翼を担っていたのです。
飛脚の真実:走るだけじゃない、物流のプロフェッショナル
● 飛脚=走る人ではなかった?
多くの人がイメージする「走って届ける飛脚」とは異なり、実際は馬による輸送も多く、荷物の安全を最優先する厳格な仕事でした。目安表に従い、時間通りに届けるプレッシャーも相当なもの。
特に「走り飛脚」は、借り物の馬に頼れない状況で登場し、人間の脚力で江戸と京都間をたった3日で移動したとの記録も!
● 科学が明かす“ナンバ走り”の効率性
走り飛脚の動きは「ナンバ走り」と呼ばれる独特なフォームで、現代のスポーツ科学でも再現されました。体の左右のブレが少なく、足の設置時間が長いことで安全性が高いのが特徴です。
この走法のおかげで、悪路でも確実に荷物を届けられたとのこと。
● 幕末の災害対応でも活躍
安政の大地震では、津波の被害を15日で出羽国まで伝えるなど、飛脚の役割は情報伝達の最前線でもありました。現代の「宅配便」や「速報メディア」に通じる存在です。
まとめ:無名の職人たちが支えた江戸の“知”と“物流”
今回の放送を通して、「江戸の出版と物流を陰で支えた職人たち」の驚異的な技術と誇りが明らかになりました。
木版の一彫り、紙一枚に込められた工夫、走り方一つに至るまで、どれも日本文化の底力を感じさせるものばかり。まさに「仕事人たち」がいたからこそ、江戸の知識と情報は日本全国に広がったのです。
歴史探偵でおなじみ、河合先生のベストセラー書籍です。